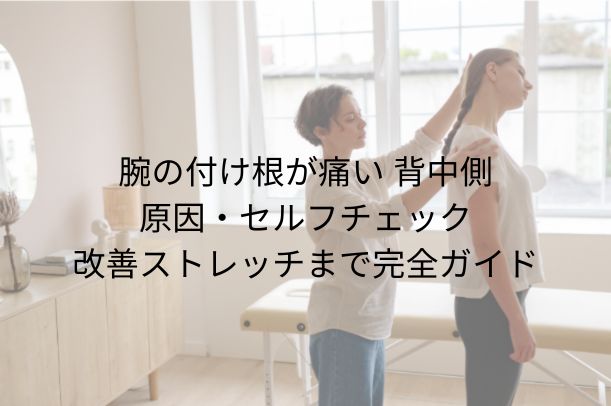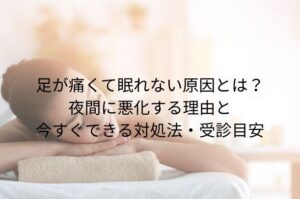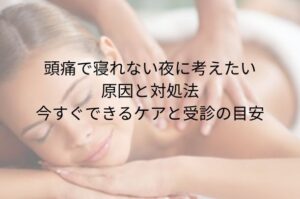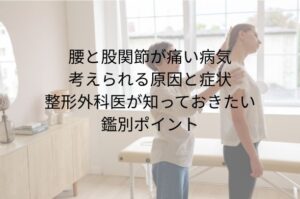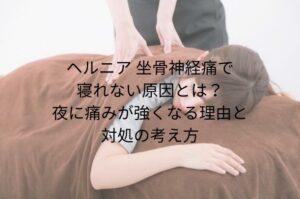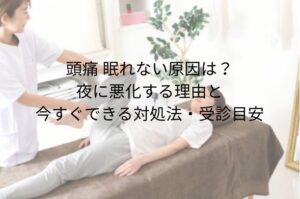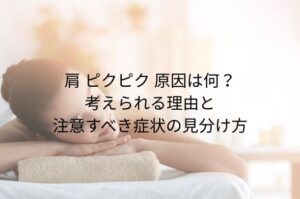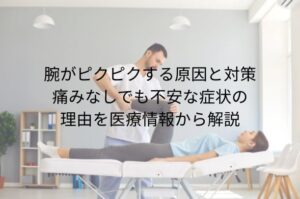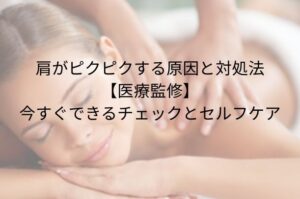腕の付け根が痛い 背中側でお悩みの方へ。症状から考えられる原因(肩関節・首・神経・姿勢など)をわかりやすく解説し、自宅でできるセルフケアと専門医の受診目安も紹介します。
① 原因を知ろう:腕の付け根が背中側に痛むメカニズム

腕の付け根の背中側にズーンと痛みを感じたことはありませんか。肩の後ろあたりに違和感があると、つい筋肉痛や寝違えだと思いがちですが、実は肩関節や首の神経など、複数の要因が関わっていることがあります。
最も多いのは「肩関節周囲炎」と呼ばれるもので、いわゆる四十肩・五十肩と重なる症状です。肩を動かすと関節を包む膜が炎症を起こし、背中側にも痛みが放散することがあります(引用元:https://www.ymo-hospital.jp/medical-content/frozen-shoulder/)。また、腱板と呼ばれる筋肉群の一部が傷つく「腱板損傷」や「滑液包炎」でも似た痛みが出ます。これらは腕を後ろに回す動作でズキッとするのが特徴です(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2430/)。
さらに、首の神経が圧迫される「頚椎症性神経根症」でも、背中や腕の付け根が痛むケースがあります。首を動かしたときに肩甲骨や腕の奥まで痛みやしびれが走る場合は、このタイプが疑われます(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/226)。
一方で、心臓や肺などの内臓に起因する“関連痛”が、背中や肩の奥に出ることもあります。痛みが深く広がるような感覚があるときは、整形外科だけでなく内科の受診も視野に入れると安心です。
姿勢も大きな要因です。長時間のスマホ操作やデスクワークで肩が前に丸まると、肩甲骨まわりの筋肉が常に引っ張られ、背中側に負担がたまりやすくなります(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2430/)。放置すると慢性化し、動かすたびに重だるい痛みを感じることも少なくありません。
つまり、腕の付け根が背中側に痛むときは「肩関節」「首」「姿勢」この3つを軸に原因を探ることが大切です。痛みが続く場合や夜間もズキズキするようなら、早めに専門機関での検査を受けて原因を特定することが、改善への近道といえます。
#肩の痛み #腕の付け根の痛み #背中の違和感 #四十肩五十肩 #姿勢改善
② 症状チェック:「あ、これ当てはまるかも」というサイン

腕を後ろに回すとズキッと痛む
「背中のファスナーを上げようとしたら、肩の後ろがズキッと痛んだ」そんな経験はありませんか。これは肩関節周囲炎や腱板損傷などでよく見られるサインです。腕を後ろに回したり、髪を結ぶ動作などで痛みが出る場合は、炎症や関節の動きに制限がある可能性があります(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2430/)。
夜間や安静時にも痛む
寝ているときにズキズキと痛みが強くなったり、夜に目が覚めてしまうことがあるなら、肩関節の炎症が進行していることが考えられます。四十肩・五十肩では、夜間痛が特徴的な症状のひとつとされています(引用元:https://www.ymo-hospital.jp/medical-content/frozen-shoulder/)。
首や肩を動かすと背中や腕に響く
首を左右に動かしたり、肩をすくめたりしたときに、肩甲骨の奥や腕の付け根までビリッと響くような痛みを感じる場合は、頚椎からくる神経の圧迫が原因かもしれません。しびれや感覚の鈍さを伴うこともあり、放置すると悪化する恐れがあります(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/226)。
同じ姿勢でいると痛みが強まる
デスクワークやスマホ操作など、長時間同じ姿勢を続けると痛みが増すタイプもあります。これは筋肉の緊張による血行不良が関係しており、肩甲骨まわりのこりや張りが強くなっているサインです(引用元:https://www.jets-s.com/symptom/numbness-upperbody)。
しびれや力が入らない場合は要注意
痛みだけでなく、腕や手にしびれ、力が入りにくいなどの症状がある場合は、神経や筋肉にトラブルが起きている可能性もあります。このような症状が続くときは、早めに整形外科や神経内科を受診するのが安心です。
症状を放置すると、肩関節や神経の回復に時間がかかることもあります。日常動作の中で少しでも「おかしいな」と感じたら、早めにケアを始めることが、改善の第一歩になります。
#肩の痛み #腕の付け根の痛み #背中の痛み #神経痛 #四十肩五十肩
③ 自宅でできるセルフケアと注意点

姿勢を意識して肩の負担を減らす
腕の付け根が背中側に痛むときは、まず姿勢の見直しが大切です。デスクワークやスマホ操作で背中が丸まると、肩甲骨まわりの筋肉が引っ張られ、痛みを悪化させる原因になります。椅子に深く座り、背筋を伸ばすだけでも、肩や背中の負担が軽くなります(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2430/)。
痛みのない範囲で動かすストレッチ
肩を動かさないままにしておくと、関節が固まりやすくなります。痛みの出ない範囲で、肩甲骨をゆっくり回す・腕を軽く前後に振るといった簡単なストレッチを行いましょう。無理に動かすと炎症が悪化するため、「気持ちいい」と感じる程度がポイントです(引用元:https://kabushikigaisya-rigakubody.co.jp/seitai/blog/base-of-arm-pain/)。
冷やす・温めるを上手に使い分ける
痛みの原因が「炎症」か「こり」かによって、対処法は異なります。ぶつけた直後やズキズキ痛むときは冷やし、慢性的に重だるいときは温めるのが基本です。温めることで血流が改善し、筋肉の緊張がほぐれやすくなります(引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_orthopedics/sy0699/)。
日常動作での工夫を取り入れる
荷物を持つときは片方の腕に負担をかけず、左右バランスよく持つことを意識しましょう。肩や腕を休ませる時間をつくるだけでも、痛みの回復が早まります。特に家事やデスクワークの合間には、1時間ごとに肩を動かす習慣をつけるのがおすすめです。
痛みが強いときは無理をしない
セルフケアを続けても痛みが強くなる、夜も眠れないほどつらい場合は、自己判断せず専門医へ相談を。体を守るためにも、「動かす勇気」だけでなく「休む判断」も大切です。リハビリやストレッチは、医師や理学療法士の指導のもとで行うと安心です。
日常生活で少しずつ意識を変えることで、痛みの悪化を防ぎながら回復を助けられます。焦らず、体と対話するようにケアしていきましょう。
#肩こりケア #腕の痛み #ストレッチ #セルフケア #姿勢改善
④ 受診すべきタイミングと整形外科での検査の流れ

痛みが長引く・夜も眠れない場合は受診を
「少し動かすだけで痛い」「夜中にズキズキして眠れない」といった状態が続くときは、早めの受診をおすすめします。2週間以上改善が見られない場合や、肩を動かす範囲が狭くなっているときは、放置せず整形外科を受診するのが安心です(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2430/)。
整形外科で行われる主な検査
診察では、まず問診と触診で痛みの部位や動かしたときの反応を確認します。その後、レントゲンで骨や関節の異常を調べ、必要に応じてMRIやエコー検査で筋肉・腱・神経の状態を詳しく確認します。頚椎の神経圧迫が疑われる場合は、神経伝導検査を行うこともあります(引用元:https://www.ymo-hospital.jp/medical-content/frozen-shoulder/)。
診療科の選び方と受診時のポイント
肩の痛みであっても、原因が首や神経にあるケースも少なくありません。まずは整形外科を受診し、必要に応じて脊椎や神経内科を紹介してもらうのが一般的です。初診時には「どんな動作で痛みが出るか」「いつから症状があるか」「夜間痛の有無」などをメモしておくと診断がスムーズです。
主な治療法と回復までの流れ
治療は症状の段階によって異なります。初期の炎症期は痛みを抑えるための薬や注射を行い、痛みが落ち着いてからはリハビリで可動域を広げていきます。慢性期には温熱療法やストレッチを取り入れ、肩の柔軟性を回復させます。腱板の損傷や癒着が強い場合は、関節鏡手術が検討されることもあります(引用元:https://www.ymo-hospital.jp/medical-content/frozen-shoulder/)。
放置せず、早めの行動が回復への近道
「そのうち治る」と思って放っておくと、関節が固まり、日常生活に支障をきたすこともあります。早期に受診し、原因を正しく見極めることで、治療の選択肢が広がり、回復までの期間も短縮できます。無理せず、痛みのサインをきちんと受け止めることが何より大切です。
#整形外科 #肩の痛み #腕の付け根の痛み #MRI検査 #リハビリ
⑤ 改善・再発予防のためのポイント

肩甲骨と背中をよく動かす習慣を
腕の付け根の痛みは、肩甲骨まわりの動きが悪くなることで再発しやすくなります。デスクワークやスマホ操作で肩が前に出た姿勢が続くと、背中側の筋肉が固まりやすい状態に。日常的に「肩甲骨を寄せる」「肩をゆっくり回す」など、小さな動きを取り入れるだけでも予防につながります(引用元:https://alinamin.jp/tired/shoulderblades-hurts.html)。
肩に負担をかけない姿勢を保つ
背中を丸めて座るクセや、片方の肩だけで荷物を持つ習慣は、肩のバランスを崩す原因になります。椅子に深く腰をかけ、肩と耳の位置をまっすぐに保つよう意識してみましょう。小さな姿勢の積み重ねが、痛みの再発防止に大きく影響します(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2430/)。
肩甲骨まわりを鍛える軽い筋トレ
再発予防には、無理のない範囲で肩甲骨を支える筋肉を強くすることも効果的です。腕を横に広げて肩甲骨を寄せる「肩すくめ体操」や、チューブを使った軽いトレーニングは、関節の安定に役立ちます。痛みのあるうちは無理をせず、医師や理学療法士のアドバイスを受けながら行いましょう(引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_orthopedics/sy0699/)。
定期的なストレッチと温めで柔軟性を保つ
筋肉は動かさないと硬くなります。入浴後や就寝前など、体が温まっているタイミングで軽いストレッチを行うと、血流が促されて肩の可動域も維持しやすくなります。特に背中側の痛みがある人は、肩甲骨を上下・左右に動かす意識を持つと良いでしょう。
「治ったつもり」で終わらせない
痛みが引いても、根本原因の姿勢や筋肉バランスが改善していないと再発することがあります。反対側に同じ症状が出るケースも少なくありません。完全に改善したと思っても、週に数回の軽いストレッチや肩回しを続けることが、再発を防ぐ最善策です。
日常の少しの工夫が、痛みのない快適な体づくりにつながります。焦らず、自分のペースで「動かす・温める・整える」を続けていきましょう。
#肩甲骨 #姿勢改善 #ストレッチ #肩こり予防 #再発防止