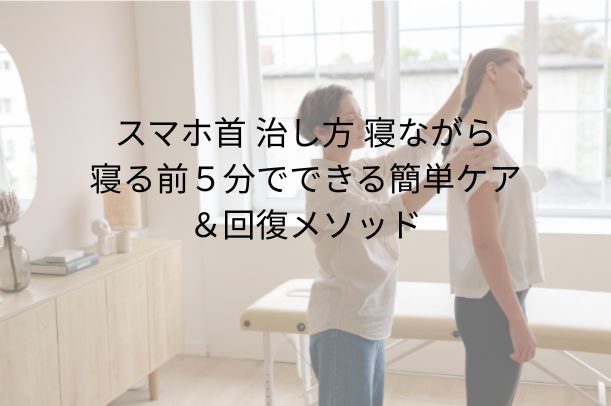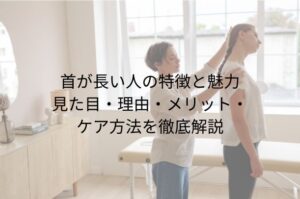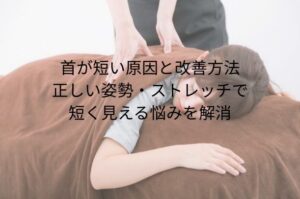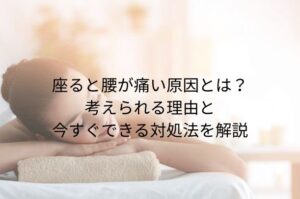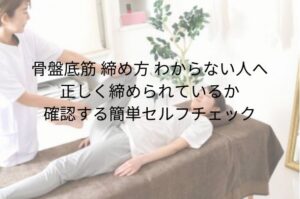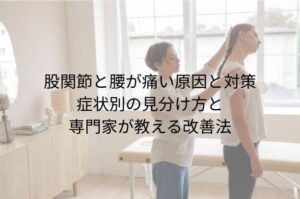2. 寝ながらできるスマホ首改善のポイント5選

① 枕の高さ・硬さを見直す
寝ている間の首の角度は、スマホ首の改善に大きく関わります。仰向けで寝たとき、首の後ろにすき間ができない高さが理想です。高すぎる枕は頭が前に倒れ、筋肉の緊張が続きやすくなります。逆に低すぎると重い頭を支えきれず、首の後ろがつぶれる形に。少し硬めの枕を選び、首全体を支えるように調整すると負担が軽減すると言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/straightneck-strech/)。
② 寝る前の簡単ストレッチで筋肉をゆるめる
眠る前に軽く首や肩を動かすことで、筋肉がほぐれ、リラックスした状態で寝やすくなります。仰向けのまま行う「チンイン(顎引き)」や「胸郭回旋運動」、肩甲骨を寄せるようにして深呼吸するストレッチなどが効果的といわれています。これらは寝ながらでもできるため、継続しやすいのがポイントです(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/straightneck-strech/)。
③ 寝る前・起きたときの姿勢リセット動作
寝る前や目覚めたときに、仰向けの状態で頭を軽く後ろへ引いてみましょう。深呼吸を数回行い、肩をすくめてからストンと力を抜くことで、首まわりの血流が整いやすくなります。眠る前に体をゆるめる習慣を持つだけでも、朝の「首が重い」「肩がこる」といった違和感が減るケースがあるそうです。
④ 寝具・寝る環境の改善
スマホ首は、日中の姿勢だけでなく寝具環境の影響も大きいといわれています。体に合わない柔らかすぎるマットレスは寝返りがしづらく、首に負担をかける原因になります。寝返りしやすい硬さを意識し、枕・敷布団・掛け布団のバランスを整えると首の自然なラインを保ちやすくなります(引用元:https://dai-seikei.com/topics/2025/06/23/introducing-how-to-fix-and-stretch/)。
⑤ 日中の姿勢・使い方もセットで改善
寝ながらケアを行っても、日中にずっと下を向いた姿勢が続くと意味が半減してしまいます。スマホを見る角度を目の高さに合わせたり、1時間に一度は肩を回すなどの工夫が大切です。イスやモニターの高さを調整し、作業環境を整えることも「寝ながらケア」の効果を高める一歩になります(引用元:https://www.ai-medical.co.jp/store/ai-media/health/13504)。
3. 寝ながらケアを続けるためのコツと注意点

① 習慣化するコツをつかむ
「寝ながらケア」は、1日だけでは変化を感じにくいもの。効果を実感するためには、無理なく続ける仕組みをつくるのがポイントです。たとえば、寝る前5分を“首リセットタイム”と決めたり、スマホを見終わったあとにそのまま実践するのもおすすめです。アラームやスマートウォッチのリマインダーを使えば忘れにくく、家族と一緒に行えば習慣として定着しやすくなります。気負わず「今日も少しだけ」と思えるペースが続ける秘訣です。
② 注意すべき寝姿勢・枕のNG例
どんなにケアをしても、寝る姿勢が間違っていると首に負担が残ることがあります。特に注意したいのが、高すぎる枕・柔らかすぎるマットレス・うつ伏せ寝など。これらは首の角度が不自然になり、筋肉の緊張を強めてしまう可能性があるそうです。横向きで寝る場合は、肩の下にタオルを敷くなどして首と背中のラインをまっすぐに保つと良いといわれています(引用元:https://ito-pain.com/blog/post-318/)。
③ 症状がある場合は医療機関の受診を検討
寝ながらケアを続けても、痛み・しびれ・めまいなどの症状が出ている場合は注意が必要です。これらは筋肉だけでなく、神経や血流の問題が関係しているケースもあります。無理を続けると悪化する可能性もあるため、症状が強い場合や長引くときは、整形外科や内科などの医療機関に相談することが推奨されています(引用元:https://nishiharu-clinic.com/2023/09/19/straight-neck/)。
④ 効果が出るまでの目安と個人差を理解する
スマホ首の改善は、個人差が大きいといわれています。軽度のケースであれば、2〜3週間ほどで首の動かしやすさや朝の軽さを感じる人もいます。一方で、長年続く姿勢のクセが原因の場合は、専門家の指導や施術を併用することで改善が進みやすいとされています。焦らず、自分の体の変化を少しずつ観察する姿勢が大切です。
⑤ 無理をせず「心地よさ」を基準にする
寝ながらケアの目的は、首を“リセット”しながら体を休めることです。痛みを我慢したり、姿勢を意識しすぎて眠れなくなるようでは逆効果。気持ちよく続けられる範囲で行い、翌朝に少しでも首が軽く感じられたら、それが改善のサインです。完璧を目指さず、日々の小さな積み重ねを大切にしましょう。
4. 寝ながら使えるおすすめアイテム&環境設定

① 枕の選び方で首の負担を軽くする
枕は「高さ」「硬さ」「素材」の3点を意識して選ぶことが大切です。高すぎる枕は首を前に倒してしまい、筋肉が休まらなくなることがあります。逆に低すぎると頭が沈み込み、首のS字カーブが崩れやすくなります。理想は、仰向けで寝たときに首の後ろにすき間ができない高さ。最近では首の形に沿って支えてくれるサポート枕も多く、タオルを重ねて微調整する方法もおすすめです(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/straightneck-strech/)。
② マットレス・敷布団の固さを調整する
首のケアには、マットレスの硬さも見逃せません。柔らかすぎると体が沈み、寝返りがしづらくなり、結果的に首や肩への負担が増えてしまいます。適度な反発力があるものを選ぶと、寝返りがスムーズになり血流も保たれやすくなると言われています。敷布団の場合も、体のラインを支えるように下に薄いマットや板を敷いて調整するだけで、首への影響が変わります(引用元:https://dai-seikei.com/topics/2025/06/23/introducing-how-to-fix-and-stretch/)。
③ 寝る前のスマホ時間を制限する
寝る直前までスマホやパソコンの画面を見ていると、首が前傾姿勢のまま固まり、筋肉の緊張が取れにくくなります。また、ブルーライトによって眠りが浅くなることもあるそうです。できれば就寝30分〜1時間前には画面から離れ、照明を落として深呼吸やストレッチに切り替えましょう。これにより、首だけでなく自律神経も落ち着き、より深い眠りにつながります。
④ 照明・部屋の温度・寝具の配置を整える
首の筋肉をしっかり休ませるには、リラックスできる環境が欠かせません。照明は暖色系のやわらかい光を使い、室温は20〜22℃前後を目安に保つのが理想です。エアコンの風が直接首に当たると筋肉がこわばる原因になるため、風向きにも注意を。寝具の配置も、寝返りしやすいスペースを確保しておくと体の緊張がほどけやすくなります。
⑤ 「自分に合う環境」を見つけて続ける
人によって快適と感じる枕の高さや温度は異なります。最初から完璧を目指すより、「少し首が楽になった」「寝つきが良くなった」と感じる環境を探ることが大切です。寝ながらのケアは、一度整えたら終わりではなく、季節や体調に合わせて調整していくことで効果が持続しやすくなります。小さな工夫の積み重ねが、翌朝の首の軽さにつながるのです。
5. よくある質問(FAQ)とまとめ

① 寝ながらだけでスマホ首は治るの?
「寝ている間に治るなら簡単」と思う方も多いですが、寝ながらケアはあくまで“改善への一歩”です。日中の姿勢やスマホを見る時間、作業環境も同時に見直すことで初めて効果が感じられると言われています。たとえば、スマホを目線の高さで見る、1時間に一度は肩を回すなどの小さな意識が大切です。寝ている間は首をリセットし、日中は負担を減らす――このバランスが鍵になります。
② 何時間寝れば首が回復する?
睡眠時間の長さよりも、寝る姿勢と環境のほうが大きく影響します。仰向け姿勢を保ち、枕やマットレスの高さを調整することで、首の筋肉がしっかり休めるとされています。寝る前に深呼吸を取り入れたり、スマホを30分前に手放したりするだけでも、睡眠の質が変わるという報告もあります。量より質を意識することで、翌朝の首の軽さにつながるでしょう。
③ 重症の場合はどうすればいい?
もしも首の痛みが強い、しびれやめまい、手の感覚異常がある場合は、無理にセルフケアを続けず医療機関に相談しましょう。神経や血流が関係しているケースもあり、整形外科や接骨院での検査・リハビリ指導が必要になることもあります(引用元:https://www.taisho-kenko.com/column/54/)。特に長期間続く場合は、早めに受診することが改善への近道です。
④ まとめ:寝ながらケア+日中の姿勢+環境整備が三本柱
スマホ首の改善には、「寝ながらケア」だけでなく、「日中の姿勢改善」「環境づくり」の三本柱を意識することが大切です。
寝る前の5分ケアを習慣化し、仰向け姿勢・枕調整・スマホ使用の見直しを行うことで、首まわりの緊張を少しずつやわらげられると言われています。
「今日から始められること」を一つずつ取り入れるだけでも、未来の体は変わります。明日の朝、首が少し軽く感じたら、それが最初のサインです。
#スマホ首 #寝ながらケア #ストレートネック改善 #姿勢リセット #首こり対策